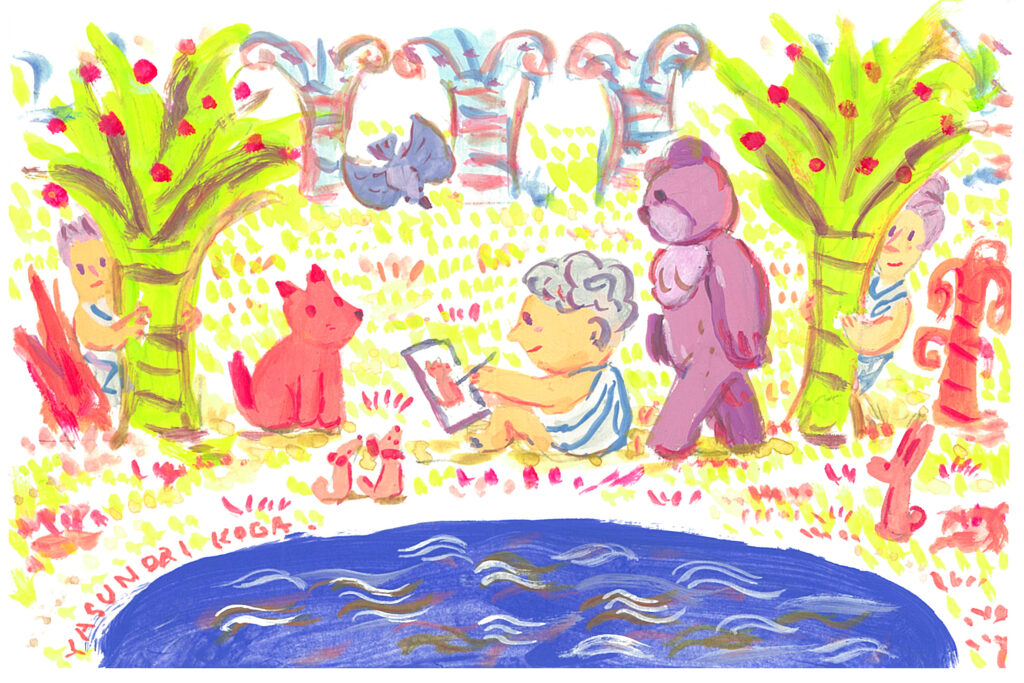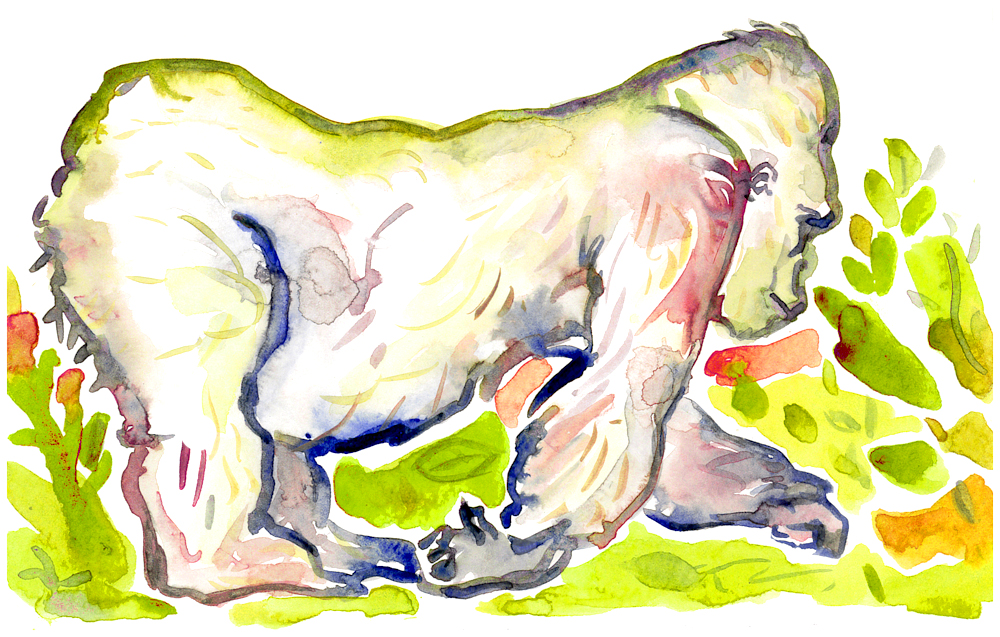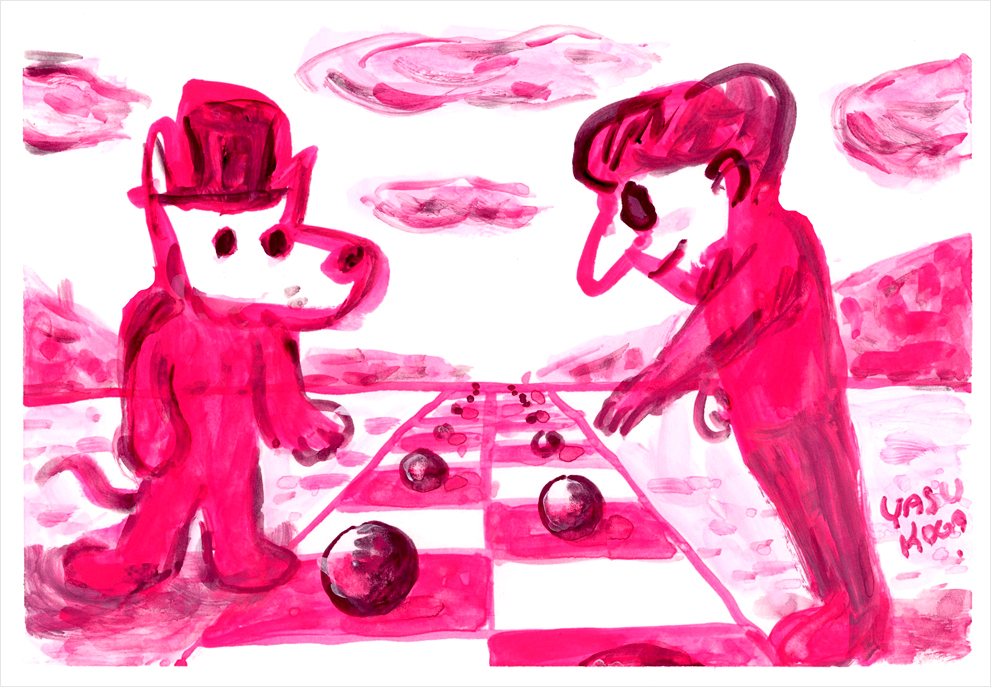
赤と黒のルーレットで、赤が5回続けて出る確率はしばしばある。でも100回続くことは生きているうちにはなさそうです。1000回続く確率はほとんど無いと言えるほどに低いでしょう。しかし、もし仮に999回赤が続いて、次にも赤がでる確率といえば、やはり50%ということになる。1000回続く確率がほぼないに等しいのに、次に赤が出る確率は50%。ここに確率論のパラドクスがあります。
人は知らぬ間に確率でものを考えるようになっています。そうして先を予測しながら生活している。ある程度あたる確率を採用(あるいは低い確率を無視)している。いや、採用した確率が「あたるように生きている」と言ってもいいかもしれません。赤だけ10回は続きにくい。100回はほぼありえない。確かに。しかし目の前のチャンスである「次の一回」だけに絞れば、100回の確率に支配されない次元が広がっています。思った以上に確率は高い。個別的な事例を大きな確率論から切り離すことで、チャンスは自分のものになる。
ちょっとややこしい言い方だったかもしれません。とにかく一般的に出来上がっている「確率的な常識」は、個人の確率にはあてはまならないということです。この一般的な確率論から自分を切り離すことで、それまでありそうもなかった「成功の確率」が格段に上がるのことになります。
確率論そのものは強力で、まとまった情報をたよりにすれば“まとまった結果”が予測できます。でも、個別事例に対してはあまり役に立たない。その意味では個人の自由とは「一般化した確率論」(常識)に支配されないということなのかもしれません。個々人のチャンスは、諦める理由が見つからないほどに可能性に満ちているのです。
AUTOPOIESIS 127/ illustration and text by : Yasunori Koga
こがやすのり サイト→『Green Identity』