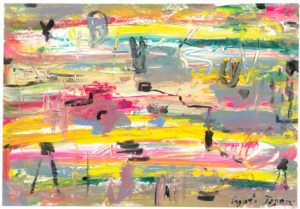内閣府が発表した引きこもり者数は、若者と中高年を合わせて110万人。すでにカウント漏れの話しもあるので、予備群を合わせると200万人いるのではなかと推測されます。一般に「引きこもり」とは「社会不適合者」と考えられています。しかしその数が100万人を超えたとなれば、「人々が社会のあり方にNGを突きつけ始めた」と考えてよいと思います。社会を舵取りする側としては、この引きこもり者数を「社会不適合者」とみなす発想は捨てて、社会の腐敗度(質的劣化)を、正確に把握し分析する必要に迫られていると考えるべきです。
そうはいっても、社会適応者のほうが多数であり、引きこもりは少数。社会を少数の者たちに合わせるわけにはいかない、という発想もあるでしょう。しかし今の社会を放っておくと、さらに引きこもりの数は増えて、最後には数が逆転してしまいます。そうでなくとも、少数者に社会を合わせることがおかしいと考えること自体が矛盾をはらんでいます。なぜなら現在の資本主義経済社会は、ごく少数の巨大資本家のために世界中の人々が苦しみながら働いているという構造なのですから。
リンゴ箱にリンゴが詰まっているとします。その箱を密閉して放置する。そうすると中は暗く風通しもわるくなる。そのうちリンゴの一部にカビが生えてきます。一部だからと無視していると最後は全体にカビが蔓延する。何故カビが発生するかといえば、リンゴ箱の環境が悪いからです。構造が閉鎖的で外と内の循環がない。この箱内の環境をクリーンに保つことでカビの発生は防がれる。カビの発生をカビのせいにしても問題は解決しません。少なくともそう考える人はリンゴの生産者にはなれません。
カビを例に環境の劣化を表現しましたが、引きこもりをカビなどとは思っていません。むしろ引きこもりを発生させる環境を作ってしまう「原因」(舵取りのまずさ)がカビだと考えられます。こういった「閉鎖構造内が腐敗する現象」は社会だけでなく、より小さな家庭などにも見られます。一つの家庭の構造(考え)が閉じて、その中の環境が悪化したとき、家族のだれかが引きこもり(あるいは正常でない状態)になる。その数が全体として110万という数字として出る。しかし家族だけが問題ではなく、やはりその家族は社会との関係で構造を閉じることになっている。むしろ家庭が社会と関係をもちながらも独立している家庭のほうが、引きこもりは発生しにくいと考えられます。平たく言えば「世間従属型の家庭」のほうが、引きこもりが発生しやすい。
何かに従属した家庭(社会)には、適切な舵取りというものがありません。ただ従うだけです。個々人よりも大きなものに従うだけです。そのうちに個人に異変が起こる。しかし大きなものに従うことを辞めることはできない。というよりは、従ているという自覚すら消えている。だからこそ、問題が起きれば個人の問題だとしか考えられない。例えば子供が引きこもりになって、親が自分が悪いんだと考えることも、個人の問題にしているので解決が難しい。この問題は環境問題であり、従属の問題です。世間に従う、科学に従う、宗教に従う、あるいは組織やグループに従う。それ自体は個人の自由なのですが、「適切な距離」を保たずに従うと、その内部は腐敗するという現象が起こるということです。
内閣府は引きこもり者数を把握しました。これを「新し社会的な問題」と定義づけしたようです。しかし「社会的な問題」ではなく、すでに「社会」自体が問題です。どんなリンゴを箱に入れても、リンゴに異常が発生する。これは、リンゴ箱という社会が「腐る装置」になって来た証拠です。これまでリンゴ箱を管理してきたのは一体誰でしょうか。現在のリンゴ生産者が責任を持たないならば、「新しい生産者」にリンゴ箱を管理してもらいたいと思うのは当然の流れでしょう。
AUTOPOIESIS 0029./ painting and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』