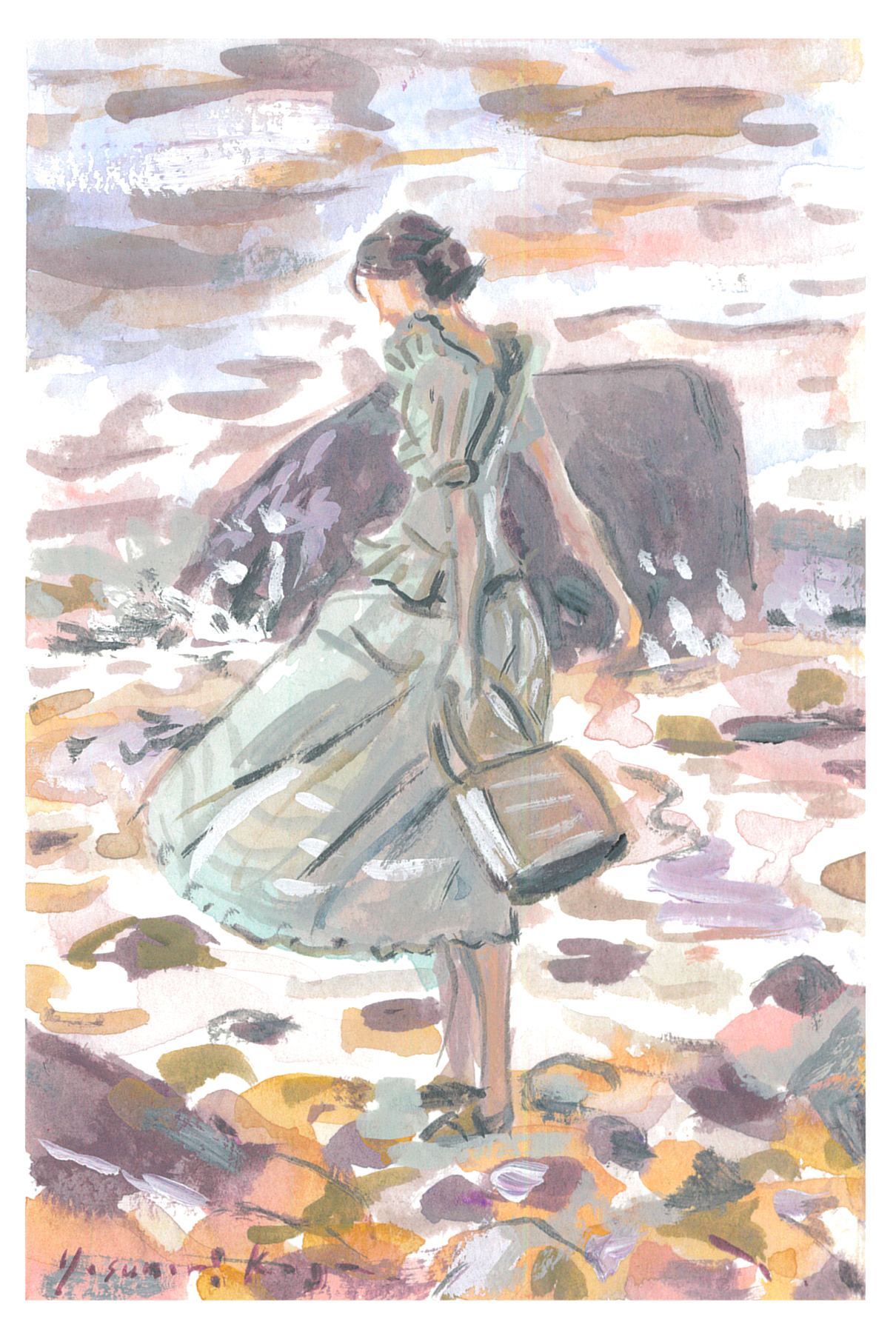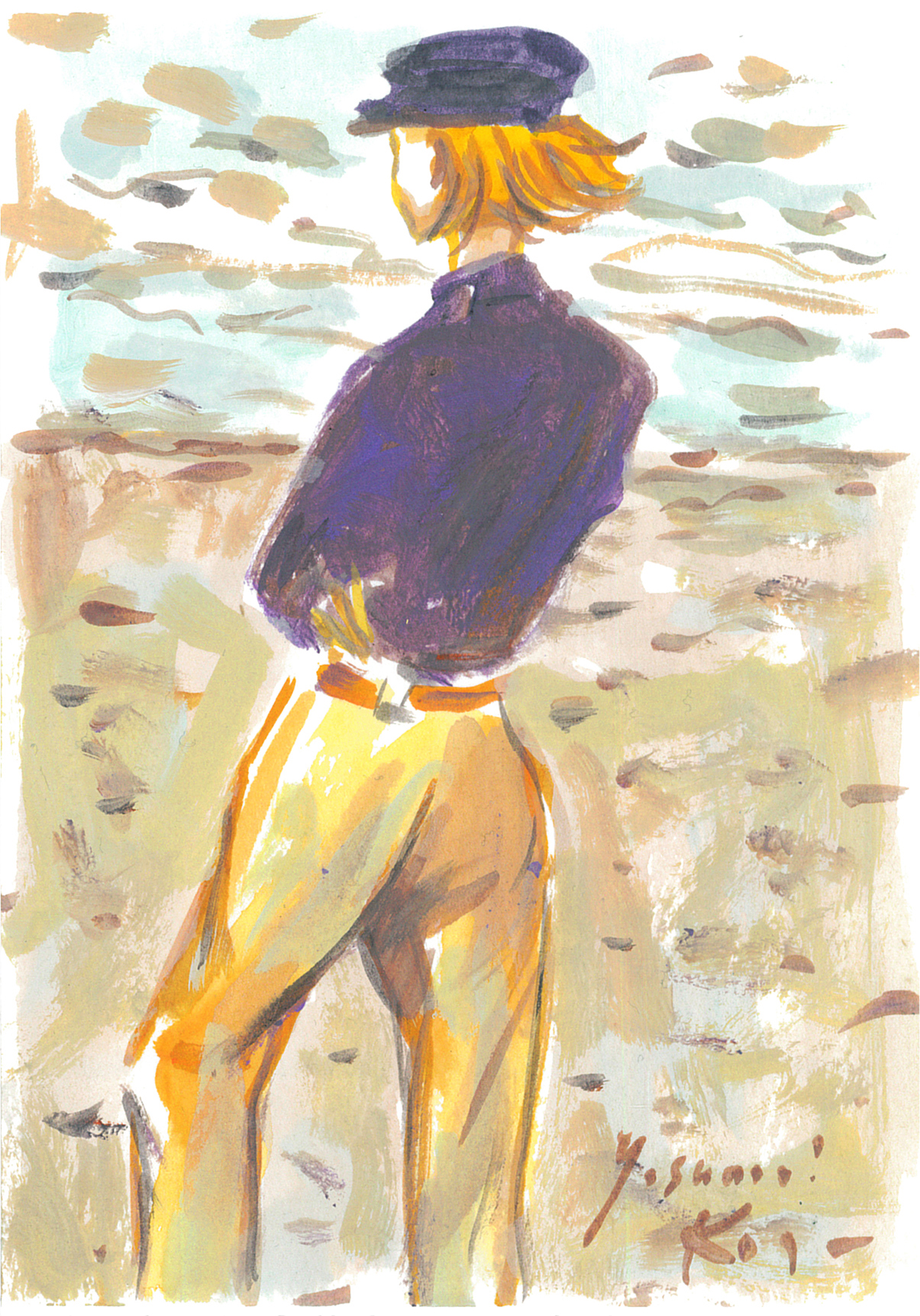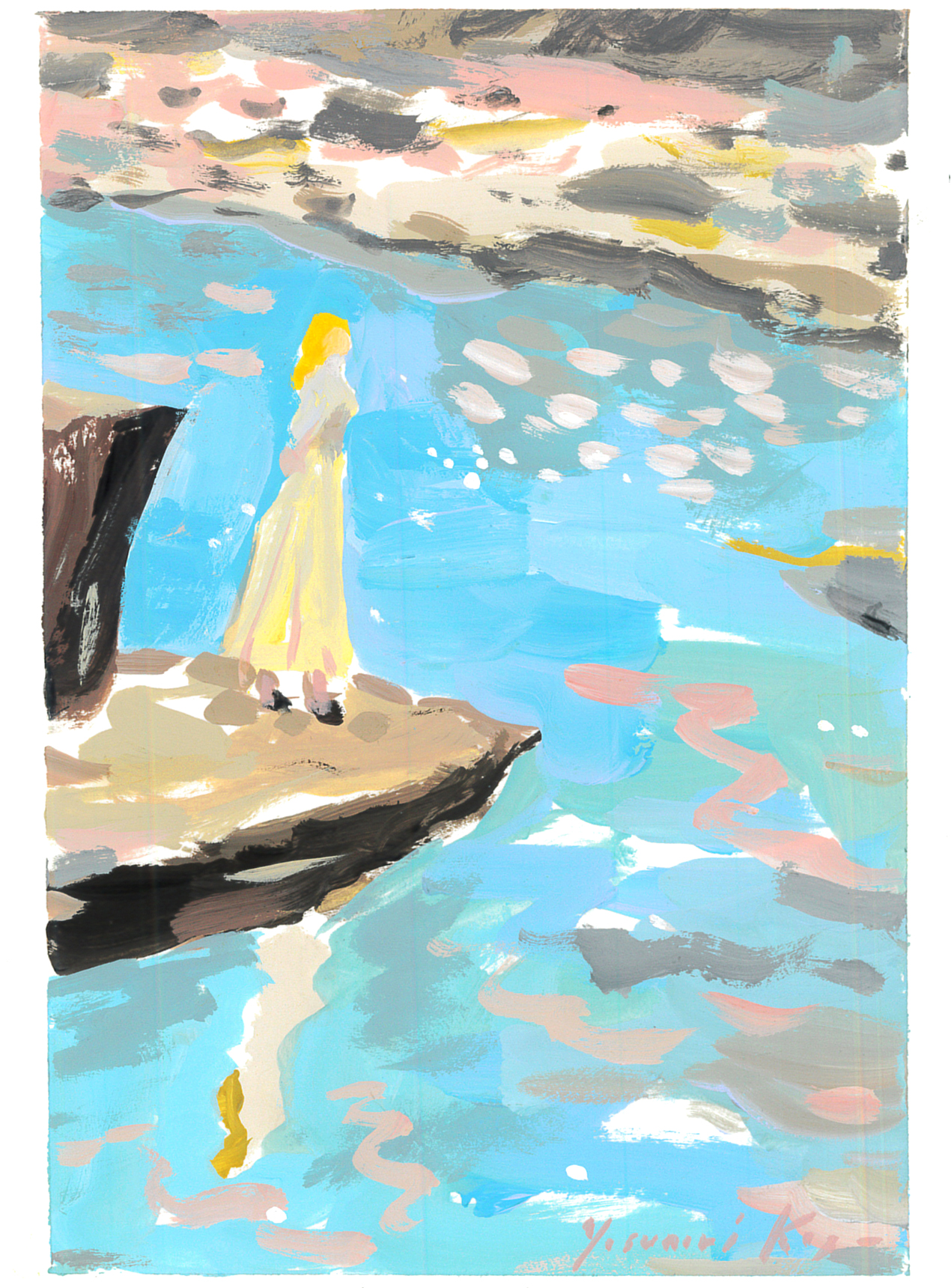
一般にファンタジーとは空想や幻想の世界、神話や童話にあるような非現実の世界と理解さてれいます。たしかにファンタジーの世界は現実にはあり得ないものばかりです。しかしファンタジーの「役割」は現実的なもの。こどもは剥ぎ出しの現実に放り出される前に、ファンタジーという現実を豊かに暗示する「メタフィジカルな世界」に親しむ必要があります。また大人になっても映画や文学などでファンタジーに触れ日常のストレスを発散するひともたくさんのいる。
こう考えるとファンタジーには「自我を守る機能」(傾いた自我を補正する機能)があることが分かります。理不尽な現実から心を守るシェルターとなりえるものが良質のファンタジーであり、特に子供が大人になる大事な時期に必要不可欠なものです。しっかりとファンタジーに守られた時間があれば、自我は柔軟性をもち、現実と創造性の二つのチャンネルを自由にオンオフできるようになる。
現実と創造性のチャンネルがないと、片方が片方を否定する安易な一元論になります。すると現実で危機的な問題が発生するとファンタジーという足場がないので妄想性の障害が出やすくなります。妄想とは現実の豊かな暗示のない世界です。さらに全てを捨てて更地にしないと問題が解決しない場合(頭では解決不能な飽和状態の時)に、創造性が必要になり、チャンネルがないと破堤します。このように次元を超えた解決や前進が必要なときに創造性(ファンタジー)の「現実的な価値」が出てくる。ファンタジーは創造性を育み、現実を新たに組み替えるための豊かな泉である。この泉を豊かにしておくことが、心と世界の長期的な安定に繋がるのです。
AUTOPOIESIS 280/ illustration and text by : Yasunori Koga
こが やすのり サイト→『Green Identity』