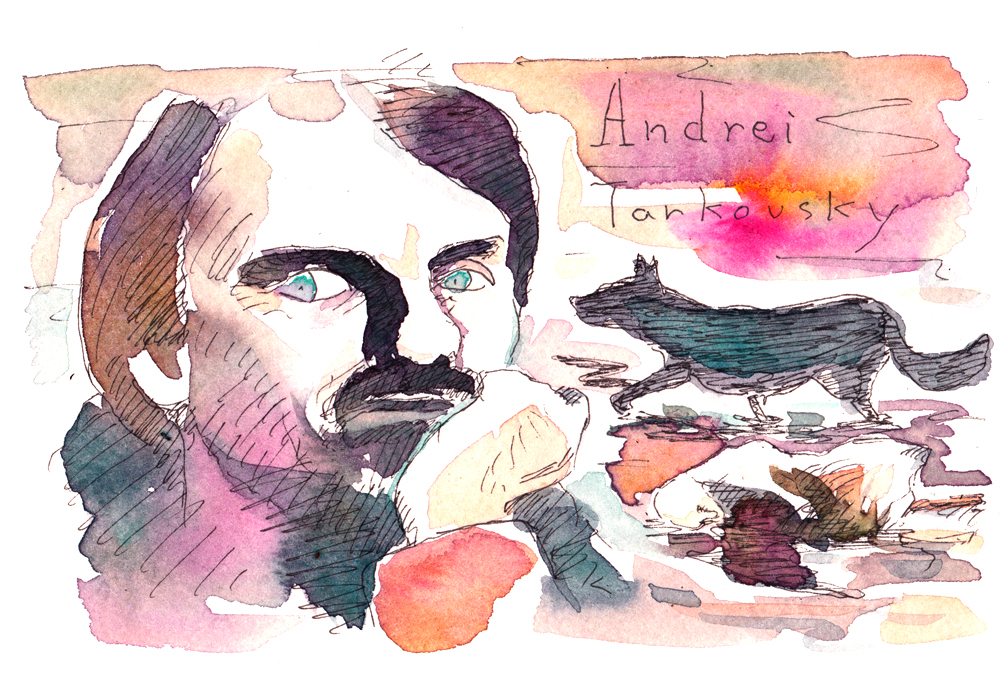物事には必ずメリットとデメリットがあります。どれを選んでも二つがワンセット。もしデメリットを避けるとメリットも消えてしまいます。よって自分に合ったワンセットを選ぶ必要がある。しかし自分の中で価値観が二つに割れていたらどうでしょうか。たとえば「自由」と「安定」の二つを“同時に”求めている状態。この二つはお互いに逆側のデメリットを補う関係にあり、片方を選ぶことがもう片方のメリットを捨てることに繋がります。こうなると、どちらも選べなくなり物事が進まなくなります。
デメリットを避けるような発想だと、必ず逆側の価値観が頭をもたげ邪魔をしてきます。そうして同じところを行ったり来たりで進まない。このような状態が限界に来たときにとられる安易な解決法が、どちらかを“無理に”バッサリ切り捨てるというものです。これは一見きっぱりとした決断に見えます。しかし、それは葛藤からの逃避であり、残った方のデメリットを受け入れていないので、また逆側の価値観が現れます。
ここにあるのは、デメリットを極端に避けることによって発生する「負の二分法」です。受け入れきれないデメリットをカバーするために、反対の価値観を求めて方向が二分してしまう。しかし本来デメリットは、ワンセットであるメリットによってカバーされなければなりません。たとえば水と油は攪拌すると乳化作用で一つに統合され「新しい性質」をもちます。デメリットの否定ではなく、メリットとデメリットを統合することで、デメリットは新しい「質」へと変化する。そこに安定した形があるのです。
AUTOPOIESIS 140/ illustration and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』