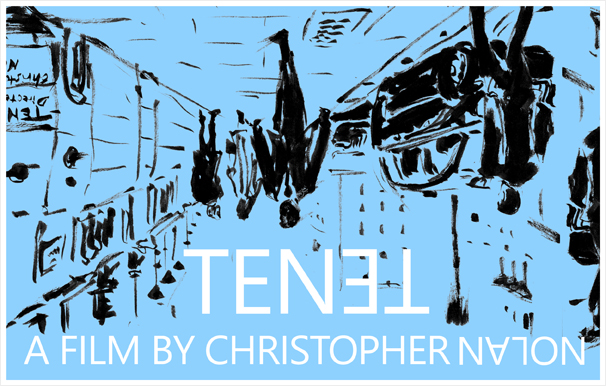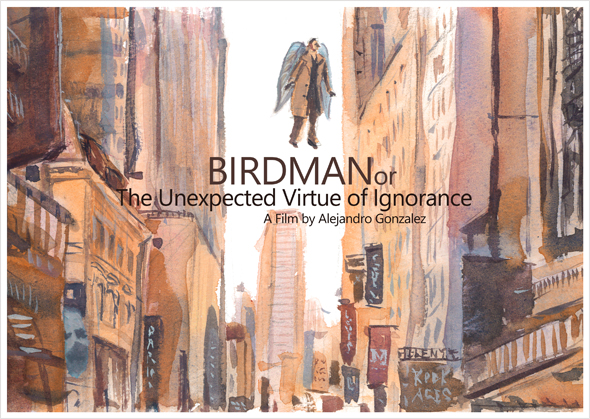【あらすじ】
現在の地球を支配しようとする未来人。それを阻止すべく結成された組織「テネット」。主人公はテネットに入り「時間を逆行する弾丸」を目の当たりにする。エントロピーを下げることで時間が逆行する現象は、未来人が作りだした回転装置により発生する。地球の支配をもくろむ未来人は、武器商人セイタ―に、現在の人々を破滅させる装置の起動を命じている。主人公は回転装置を使って時間を逆行し、セイタ―を阻止しようとする。しかし時間を先行するセイタ―は常に主人公の先回りをすることになる。
【時間の逆行可能性】
この物語では、時間が逆行できるのは回転装置を通過した物に限られている。つまり起きた結果を起点としてのみ、時間をターンできるのである。これは、結果がある時のみその原因を導き出すことが出来るという意味でもある。時間を逆行する映像はなかなか衝撃的であるが、しかしこの映画に潜む真のテーマは「情報」であり「決定論的な因果性」を突破する話しである。
登場人物の一人ニールの「起きたことは仕方がない」というセリフがあるように、結果を受け入れることで逆行が可能となるだけでなく、そこから新しい分岐が可能となる。その意味では目的論を示唆したセリフでもある。さらに主人公は「無知こそ最大の武器」と語る。これは「反決定論」を指すもので、「反情報化」という“自由”を示している。つまり情報化されている間は先回りされるのだ。
そもそもエントロピーを下げることで「時間が逆行して見える」という設定は、起こったことの情報化を示すもである。なぜなら情報とはエントロピーの逆数だからである。物語中でも物理学や量子力学が持ち出されているが、ノーランがそれらの下敷きにしたのは精神分析学ではないだろうか。フロイトは、結果がある時だけ原因を見出すことが出来るという。そして隠れた過去の原因を、現在の自分が真に認識しえたとき、心的外傷は消えるとしている。これはまさに、未来の自分が時間を逆行して、過去の原因に対して「起きたことは仕方がない」という受け入れを行ったことに等しいからである。
フロイトの場合は「事実認識」によって停滞した流れを正常化させるという原理がある。『TENET』における「時間の逆行性」も同じく、現実の受け入れによって「新たな可能性」が初めて生まれることを描いている。そもそも未来人が現代人を破滅させれば、未来人自身も破滅するという「オイディプス理論」が成り立つ。しかし未来人もその理論(決定論)を超える結果を期待して、計画を遂行しようとしているのである。つまり結果から原因へ逆行し、決定論を超える新たな流れを作り出そうとする。それは先の分からない展開の「創造」である。この創造的計画を阻止するには、それを超える計画が必要となる。その作戦は過去と未来の二つが「統合」される場所(10分間)で展開されることになる。その意味では『TENET』の二つの「TEN」に重なる「N」を「NOW」と受け取りたい。見事な傑作である。
vol. 047 「TENET テネット」 2020年 アメリカ・イギリス 151分 監督 クリストファー・ノーラン
illustration and text by : Yasunori Koga