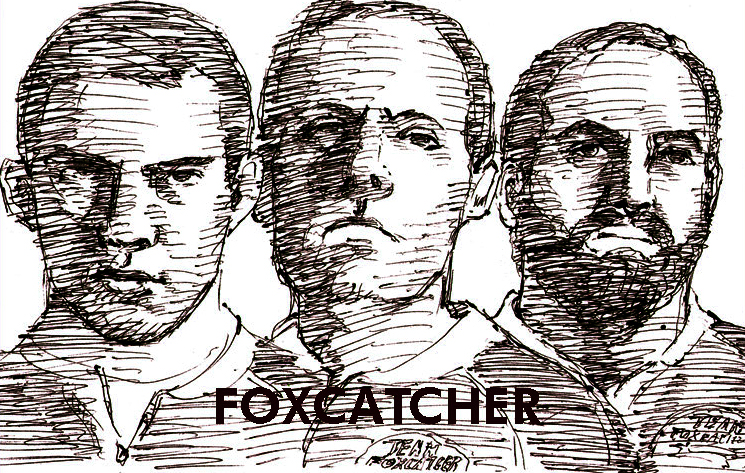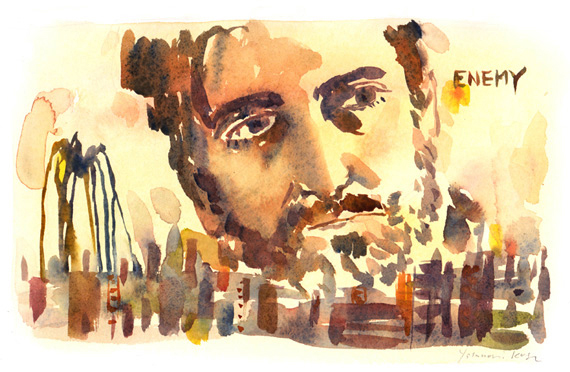“とってもつれない女”アンジェラは、デンマーク人のエミールと同棲中。ある日、半熟卵をつくる代わりに子どもがほしいと訴えるアンジェラ。 エミールは結婚してからだと突っぱねる。それでも食いさがるアンジェラ。誰でもいいならと、エミールは日ごろアンジェラにちょっかいを出しているアルフレードを呼びつけるのであった。
ジャン=リュック・ゴダールの監督第三作目にして初カラー作品。話はとてもシンプルな三角関係。そんな物語を、斬新な編集と、意表をつく音楽が屈折させていく。この手法が主人公アンジェラの移ろいやすい性格とマッチしていて面白い。トリコロールを基調とした洒落た美術は、ベルナール・エヴァン(シェルブールの雨傘)が手掛けたもの。「悲劇か喜劇かわからなくなったが、とにかく傑作だ」というエミールのセリフがそのまま当てはまる、愛すべきコメディーである。
vol. 035 「女は女である」 1961年 フランス・イタリア 84分 監督ジャン=リュック・ゴダール
illustration and text by : Yasunori Koga