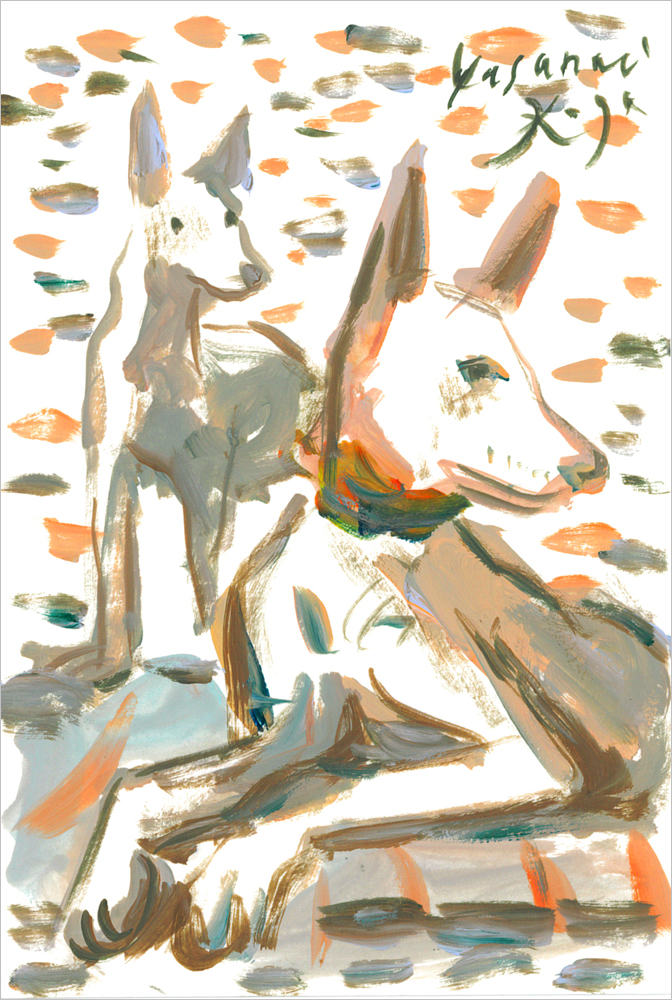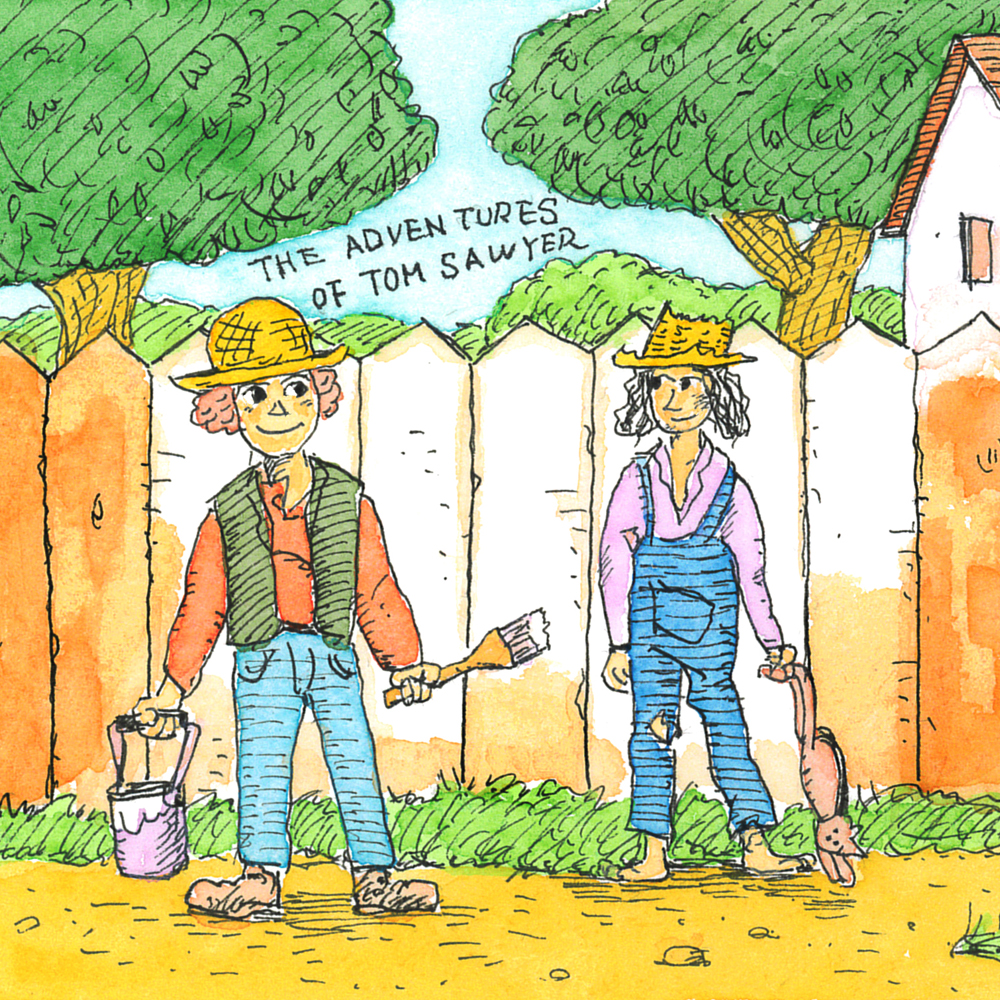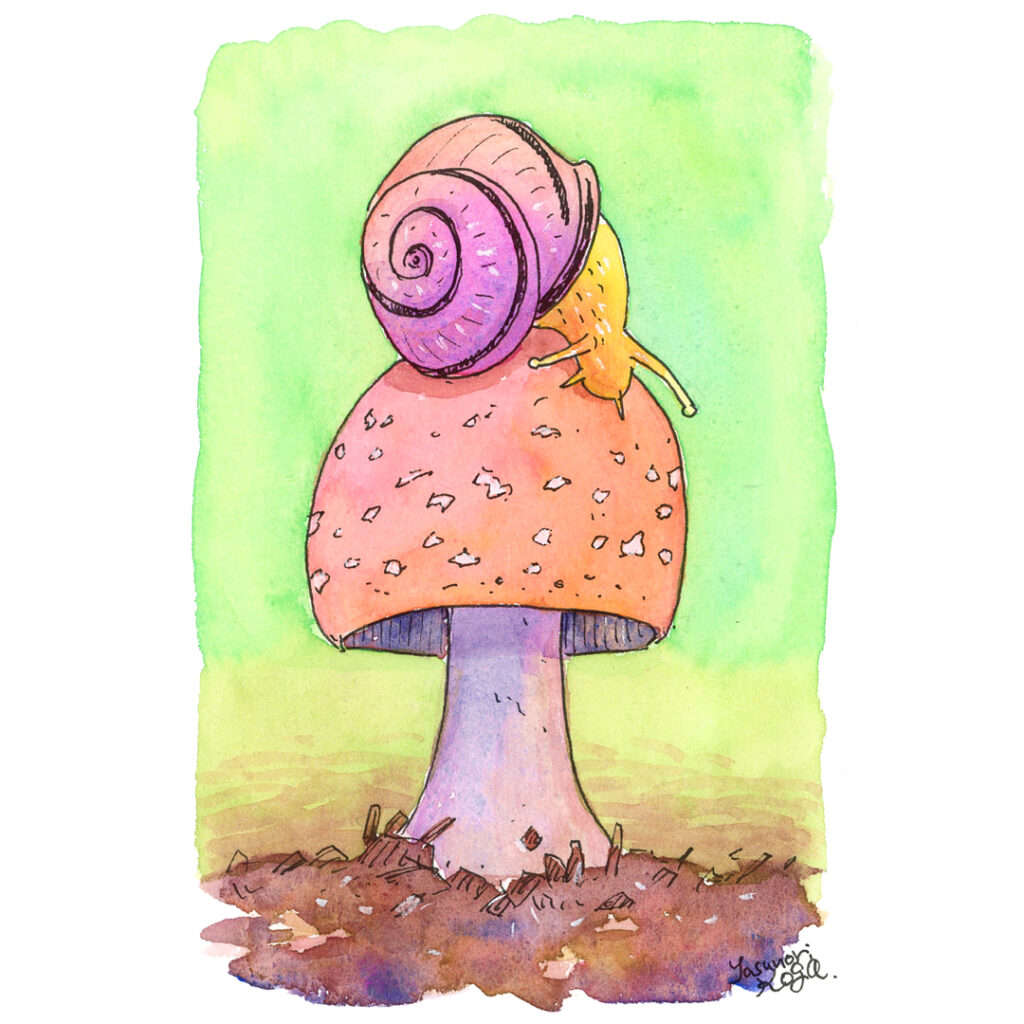生態学には「棲み分け」という言葉があります。例えば川魚のイワナは冷水を好むので、最上流に生息し、それより下流にヤマメが生息し争いが避けられる。この状態が「棲み分け」です。これは言い換えると「環境の違い」があることによって、性質の違うもの同士が争うことなく存在できることを示しています。逆にいえば、本質的に性質の違うもの同士が、同じ環境を求めていると争いが起こるということです。
人間は他の動物と違いそれぞれに個性を持っています。性質がいろいろと違っている。なのでもし性質の違いを無視して、みなが同じ環境を望むとすれば、争いや問題が起こります。生態学の世界では、性質の違う生物が一か所に集まると爭いや排除が起こると言われています。つまりみんなと同じ環境や同じ状態を望むことが、争いや絶滅の原因になっているということです。その意味でいえば、一般的な価値観という一点にみんなが集まることは、実は危険なことだと考えることができます。
人には個性があり、その個性に適した環境を見つけることが大切です。自分にピッタリと当てはまりラクに過ごせる場所がある。そういった環境は大多数では形成されていません。必ず「棲み分け」は適切な数によって安定しています。ダーウィンが生態的地位(ニッチ)と呼んだ、自分に合った場所を探し出す。ただ単に「みんなと同じ」ではなく、自分自身にあった環境を見つけることが、争いやストレスから解放された生き方につながる。そのためにもまずは、自分の「本来の性質」を見つめなおすことが大切なのです。
AUTOPOIESIS 153/ illustration and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』