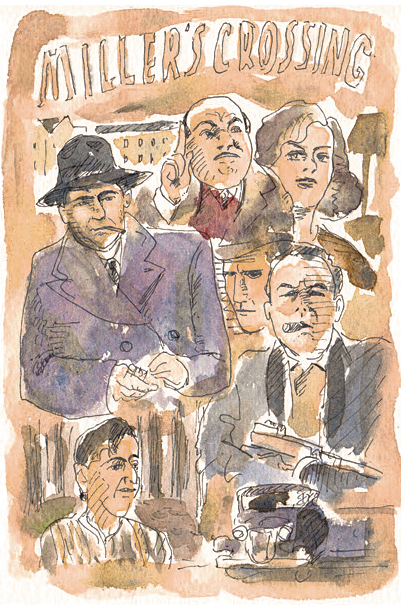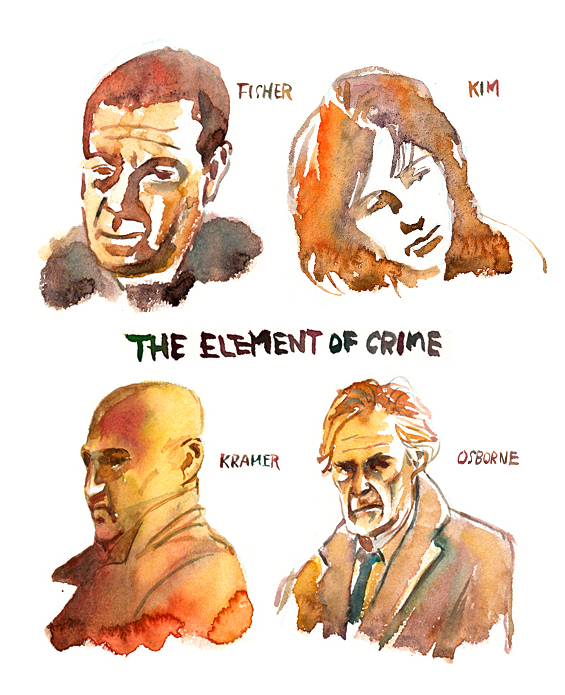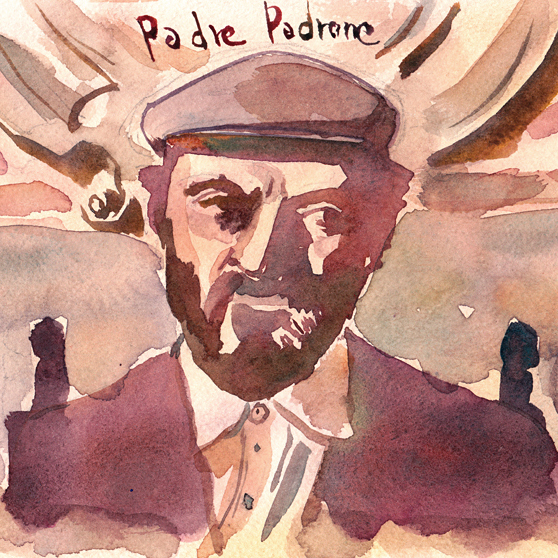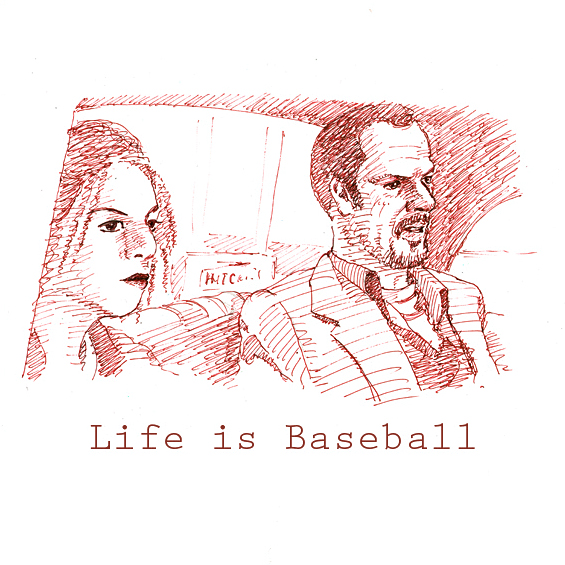『詩人の血』はフランスの詩人、ジャン・コクトーが最初に撮った映画である。制作されたのは1930年というから80年以上も前だ。もちろん現代の映画からすれば、映像はモノクロで画質も荒い。しかし内容は素晴らしい。詩人の言葉を散りばめたような詩的映像の連続である。 一般的な映画にあるような、明快なストーリーはここにはなく、ただ詩人が自分の想像力を垣間見るというもの。コクトーも自ら、非現実の記録映画だと表現している。
人間のように喋り出す彫刻は詩人にこう告げる、「お入りなさい、あなたが創造した鏡のなかへ」「それはあなたの財産」。想像力が詩人にとって如何なるものなのか。それを映画によって示そうとするコクトーは、やはり規格外の詩人である。
vol. 025 「詩人の血」 1930年 フランス 50分 監督 ジャン・コクトー
illustration and text by : Yasunori Koga