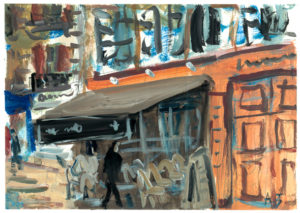人は希望がなければ無気力になります。ならば希望とはどういうものなのかを知ることで、「希望の喪失」を回避できないでしょうか。生きる気力に関わることは、カウンセラーや心療内科医といった専門化が受け持つことで、希望の分析などいまさら意味がないと思われるかもしれません。しかし人間が「積極的に生きていく」うえで欠かすことのできない希望の概念を、あやふやなままで、いくら精神病理学を適用しても効果はない、という意見も無視できません。
希望とは「未来への期待」のことです。期待とは可能性や蓋然性の問題です(これは前回考察しました)。そして、未来とは「時間」の問題です。時間を直線的に考えると「過去→現在→未来」という連続した流れになります。「過去・現在・未来」の間に、言葉の違いとしてあるような「断絶」はありません。しかし「未来への期待」とは、「まだ分からないものの可能性」つまり、現在とは連続していない所にあるものです。そこには時間的な「断絶」があります。もし未来を現在と陸続きのものとして捉えると、それは本当の(希望が発生できる)未来ではないことになります。
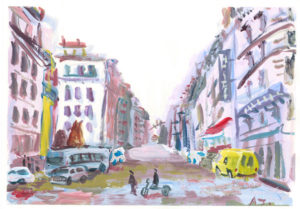
希望を「未来に咲く花」だと考えてみます。「未来に咲く花」は、現在とは断絶した場所にしか咲かない。もし断絶していた未来が、現在と陸続きになれば、未来は現在化され、希望の花は枯れてしまいます。別の言い方をすれば希望という花は、現在と別レイヤーにしか存在できないということです。それを無理に現在に植えるとすぐに枯れてしまう。「希望の喪失」はこのような「時間を連続と考えるか、非連続(断絶)と考えるか」に関わる現象でもあると考えられます。
時間を断絶する。つまり非連続として時間を感じることで、未来が純粋に確保される。実は自然の原理に従えば、そのような断絶の時間で生きることになります。たとえば人間は寿命があるが何万年も連続して生き続けています。断絶と連続の世界に生きている。そこに必然的に生まれる精神と時間のリズムが「非連続の時間性」です。その自然な時間感覚である「非連続の時間性」を疎外しているのが、人工的なパソコンやスマホ、ネット、ゲームといった「無時間性」(無変化)の世界です。これらは経済や産業と深く結びついているので容易の変えることはできません。しかし希望の花は、形骸化した資本主義(現在)から断絶した未来にしか咲かない。社会の次元が逓増していく中で、希望を既成の心理学だけでは守れなくなってきました。時間の概念を物理学やその他の視点で修正することによって、希望の花が咲く「場所」は確保されるのです。
AUTOPOIESIS 0039/ painting and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』