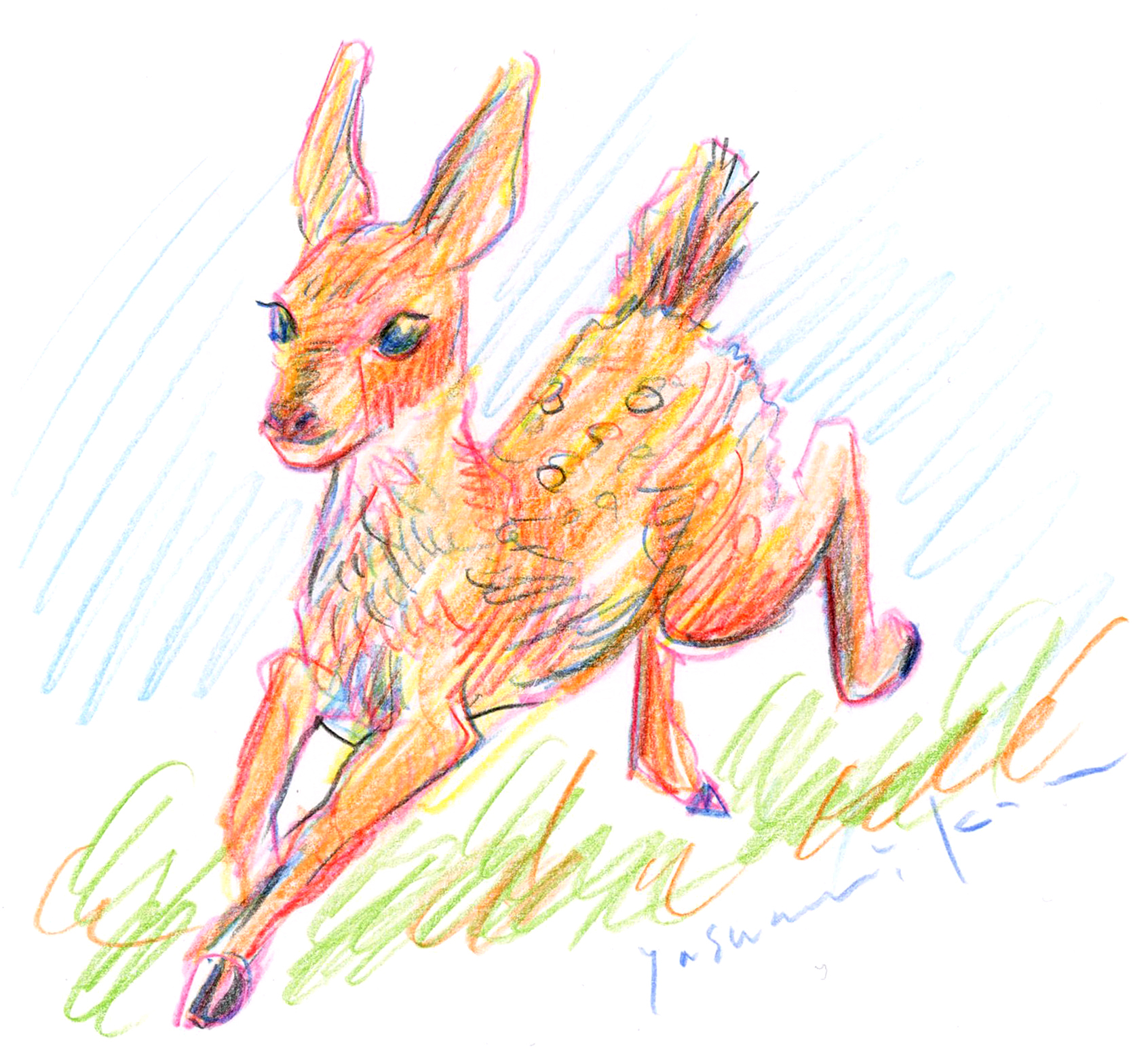一般に現実逃避という言葉にはマイナスのイメージがあります。しかし適量であればまったく問題はありません。映画も音楽も、お酒もある意味では非日常であり現実逃避です。しかしアルコールによる逃避が日常化し、現実に悪い影響を与えはじめると問題となります。あるいは、ある友人たちが現実逃避を共有する仲間だったとして、その人間関係が日常に食い込んできたときに問題が発生してくる。例えばその人たちと一緒に仕事をしだすとか、その人たちの意見で大事なことを決定するなど。これはアルコール依存で現実が侵食されることと同じ現象です。しかしそういった現象を外から正そうとしても、逃避を邪魔することになるので反発をまねいてしまう。
非日常が日常へ流入したときに問題がおこる。つまり逃避が現実を食ったときに病理(パラドクス)がうまれる。アルコールの作用が日常を歪ませ、逃避仲間が生活に影響を及ぼし、推し活が人生と入れ替わる。これらは全て日常と非日常の区別が消えてしまうことで「非現実による現実への流入」を許している現象です。二つの間にあるダム(壁)が決壊して妄想系が現実に流入している。あまりに逃避傾向が強いと逃避量がダムを超えてしまう。そうなると現実を正しく認識し、そこに幸福を作り出す(他者と上手くやっていく)ことができなくなります。
では逃避と幸福はどこがちがうのでしょうか。逃避はあくまでも非現実(現実逃避は不可能なものへの逃走)であり現実には成立しません。しかし幸福は現実にしか成立しないものです。ゆえに現実逃避を続ける間は現実的な幸福がありえません。アルコールに溺れ、逃避仲間との絆を最優先し、推し活に全てをつぎこむ間は(そうするしかない時期もあるとして)“本当の幸福”はやってこない。つまりイミテーションで手一杯のうちは本物を手にできない。そうならないためには、日常と非日常、現実と逃避の区別(ライン)をハッキリさせることが大切です。さらに現実逃避を適量にし、残りは健全なものへと変えていく。その移行先として最適なものの一つが「現実に非現実を創り出す」芸術活動なのです。
AUTOPOIESIS 239/ illustration and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』
YKアートコミューン →『YK art commune』