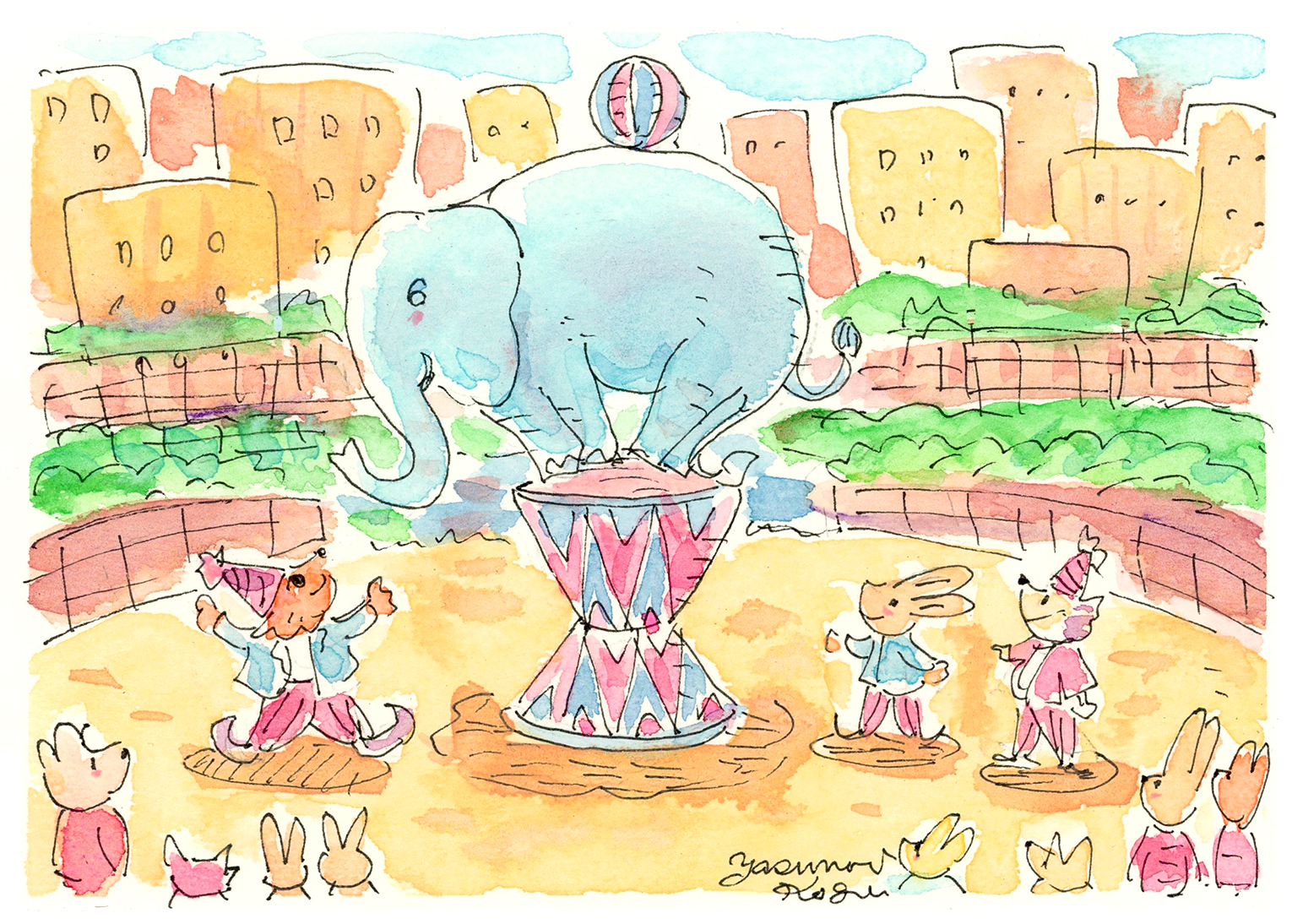「セルフイメージ」とは、自分で自分のことを「自分とはこういう人である」と思っているイメージです。つまり主観的な自分です。それに対して、客観的な「現実としての自分」が一方にあります。そしてこの「セルフイメージ」と「現実としての自分」はズレていることが多い。たとえば自分では人付き合いが苦手だと思っているのに、周囲からは人当りがよくお喋りだと思われている。こういったズレは良くあることです。では一体このズレはどこから発生するのでしょうか。
人は基本的にセルフイメージに従って行動しようとします。よって表面的には周囲からもセルフイメージに近いイメージを持たれます。しかし、長く付き合っていくと、本質的な部分が分かってきます。付き合った最初とはイメージが違う、ということは良くあることです。これは、相手がもつセルフイメージと現実とのズレが大きいことから起こります。そしてこのズレは現実の自分が受け入れられないことから、その補填として作られるセルフイメージによって発生します。なのでこのイメージが揺らぐ情報や他者は一切回避するようになります。
ではいったい、このズレを修正するにはどうすればよいでしょうか。それにはまず「現実としての自分」を再発見し、受け入れることが必要になります。たとえば物静かな人が情熱的な絵を描くことがあります。本人も物静かだというセルフイメージをもち、周囲もそう思っている。しかし絵という自己表現に「本当の自分」が現れます。この絵の情熱的な部分は、自分がこれまで抑えてきた側面であり、それを発見し受け入れることで自分の「全体性」が回復します。それとともにセルフイメージと現実とのズレも修正されていく。自己表現を通して「本当の自分」を再発見する。ここに「ありのままの自分」でいられるという、本当の意味での「自由」があるのです。
AUTOPOIESIS 194/ illustration and text by : Yasunori Koga
こがやすのり サイト→『Green Identity』