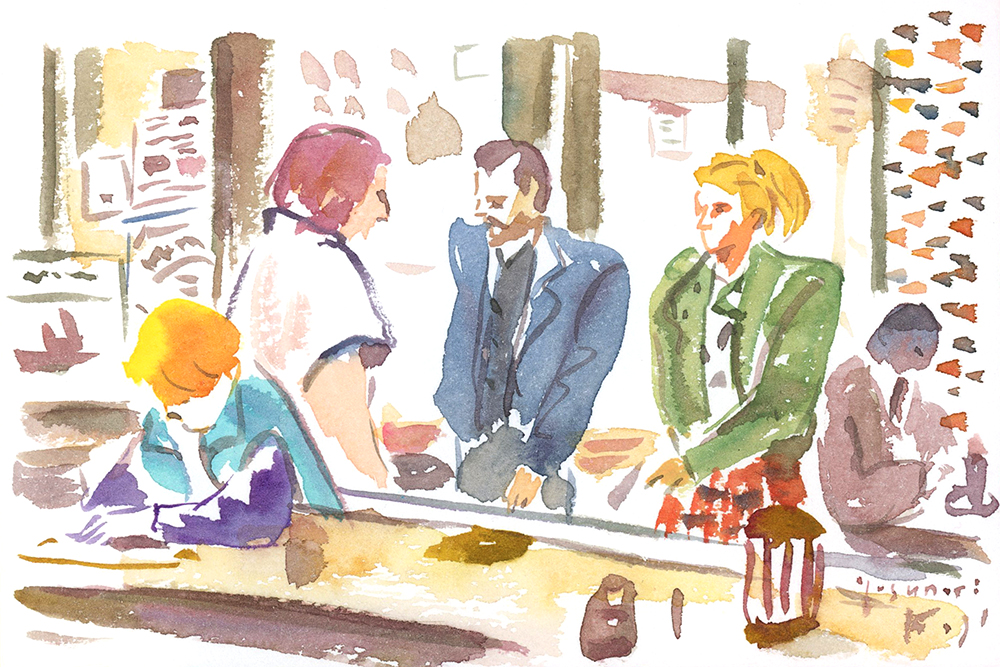人はそれぞれに価値観を持っている。その価値観は共有されることもあり、また共有されないこともある。個々の主観的な世界観は、人々に共通の客観的な世界とは違うからである。
もし自分の価値観だけを肯定し、それに当てはまらない価値観をすべて否定してしまえばどうか。客観的には自分とまったく考えの違う人がたくさん存在している。にもかかわらず、自分の世界では否定され消し去られてしまう。これは怖いことではないか。
お互いの価値観や世界観は独立している。ゆえに客観的な世界を認識することによって、初めてお互いの世界観が共有できるようになる。物を投げれば落下する。太陽は沈んでまた昇る。共有化できる客観世界(現実)は無数にあり、自分と違う価値観を持った人が存在することもまた客観的な事実である。
もし自分の価値観だけを肯定し、それ以外をすべて否定して存在を認めないとすればどうか。それは主観の世界に入り込み、客観的な事実としての世界を見失っていることになる。「繭の中の擬似現実」では、自己だけが肯定され都合の悪いものは消し去られる。しかし、客観的な現実は動かし難く存在し、また個人の主観世界を包み込んでもいる。もし「繭の中の擬似現実」が、客観的な現実とあまりにもかけ離れていれば、必ず危機が訪れる。船が現実の客観的な地図を無視すればいつかは必ず座礁するだろう。
現実の否定と繭の関係は、現実と想像力の関係に似ている。目の前にないものを見出すのが想像力。これはある意味で現実を否定したところに生まれる。しかし現実との対応関係を失った想像は「妄想」という病理学的な名で呼ばれる。繭の内側は「妄想のスクリーン」が張り巡らされている。そこに映るのは自分だけである。
外部環境から遮断され、自己をあたため守る環境は、子供が成長する過程で必要なものである。ある意味では「繭の中の擬似現実」がなければ成長できない。このような子どもに必要な擬似現実を、臨床心理学の世界ではファンタジーと呼ぶ人もいる。しかし成長過程で繭の殻は捨てられる。ずっといると危険だからである。
もし繭から出るタイミングを失うと、人は「繭の中の擬似現実」を客観的な現実と取り違えてしまう。都合のよいものしか見えなくなり、違う価値観は全て消し去られる。そして現実の世界を自分の世界へ強引に捻じ曲げるようにすらなる。ここが危険な世界への分岐点だと言える。そういった妄想への傾斜をくいとめ、自己を正しく補正してくれるのが客観的な事実認識なのである。
AUTOPOIESIS 100/ illustration and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』