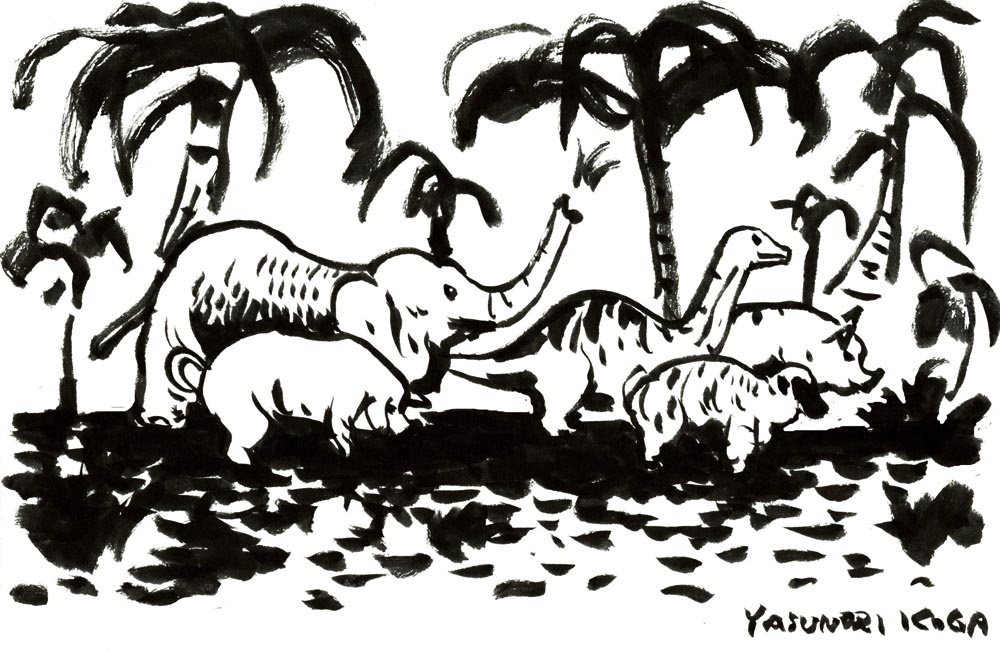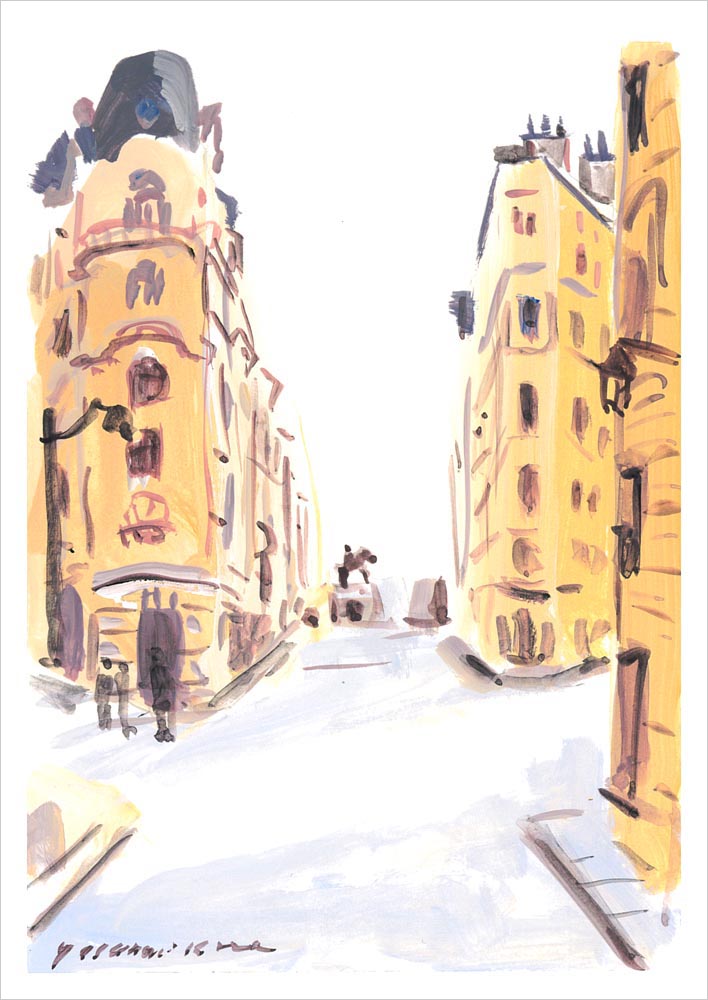人はそれぞれに違った人生を送っている。これは当然で、もしまったく同じコピーのような人間であったとしても、環境がちがうだけでそれぞれ違った人生になります。経験が違えば性格も考え方も違ってくる。出発点の個性が違えばさらに結果は違ってきます。しかし、それぞれに共通の社会的なルールを守るというレベルでは、みな同じ生き方をする必要があります。
共同で守るべき社会的なルールは、社会が円滑にゆくために、また個人がその社会で上手く生きて行くために必要なものです。そこで模範となる基準が役に立ちます。しかし細かい個人の生き方にまで標準を適用させようとすると問題が起こります。車なら時速50kmと標識がでている。しかし現実には48kmや51kmで走ることもあるし、突然ブレーキを踏むこともあります。ずっと時速50kmしかし許されていない車があれば、どこかで事故が起こるはずです。
標準的な生き方とは、概念上の目安であり実際にはありえないものです。しかしその標準に強迫的に固執すれば、その人は社会的に問題を発生させてしまいます。さらに自分の個性や人格を標準化しようとすれば、心のレベルでも問題が発生します。なぜなら自己否定になるからです。そうならないためには、まずは「社会」と「個人」の明確な線引きが必要です。そして標準という「概念上の目安」と「現実の生きた対応」との違いを明確にする必要があります。基準に支配されることなく、個人が主体性をもって基準を「適切に応用する」ことが健全なやり方なのです。
AUTOPOIESIS 145/ illustration and text by : Yasunori Koga
古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』